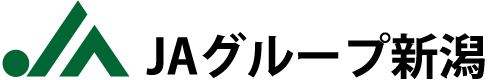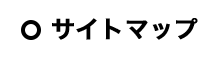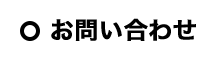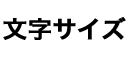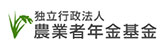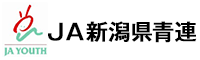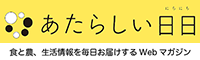水稲 初冬直まきで規模拡大 春作業の負担軽減
JAにいがた岩船研修会
2023.12.08
【にいがた岩船】JAにいがた岩船は11月中旬、関川村で県内初の「水稲初冬直まき栽培研修会」を開いた。県内外の生産者や、自治体など関係機関の職員ら100人が参加。実演や講演などを通して、初冬直まきの有効性を確認した。
実演は、初冬直まきに2022年から取り組む(有)上野新農業センターの圃場(ほじょう)が会場。機械で施肥、耕起、播種(はしゅ)、鎮圧まで1工程でする作業を見学した。
同社は19年から春の直まきにも取り組み、23年は、耕作面積48ヘクタールのうち12ヘクタールで直まきをする。直まきでは12ヘクタールのうち、2・5ヘクタールで「つきあかり」を初冬直まき。10アール当たり8・5俵(1俵60キロ)を確保している。
JAにいがた岩船営農企画課の山田薫係長は、初冬直まきについて「積雪で春作業の期間が短く、規模拡大が進む中では春作業の負担が非常に大きい。作業を前倒しすることで、省力化や作期分散にもつながる」と話す。
岩手大学農学部の下野裕之教授は、初冬直まきの全国状況などを紹介。「11、12月に作業を分散することで、機械購入など新規投資をしなくとも規模拡大ができる。担い手の高齢化、農地集積が進む状況で、一つの選択肢として初冬直まきの技術を得られれば経営の幅が広がる」と指摘した。
農研機構中日本農業研究センターは、県内で栽培する際のポイントを説明。各メーカーは直まきに適した肥料や除草剤を提案した。
同社の大島毅彦社長は「受託面積の増加で育苗ハウスが限界。今後増える面積も、直まきで対応する予定」とする。「初冬直まきは種子更新の課題があり、その課題がクリアできればぜひ増やしていきたい」と期待を込めた。
写真説明=1工程で初冬直まきを実演する不耕起の圃場(新潟県関川村で)
R5.12.5 日本農業新聞掲載記事
JAにいがた岩船